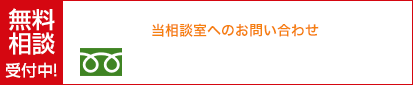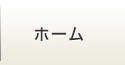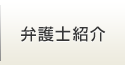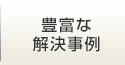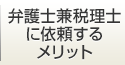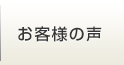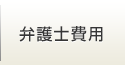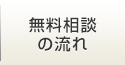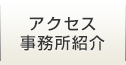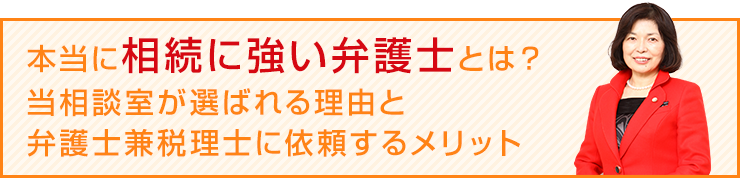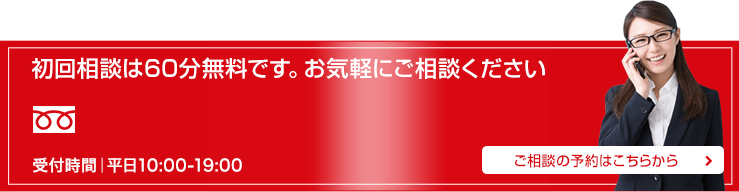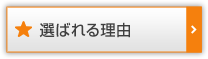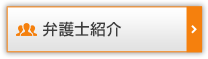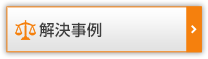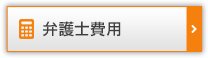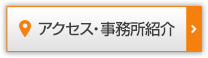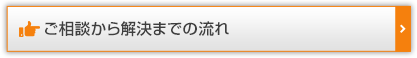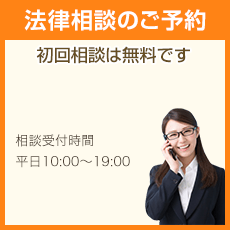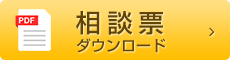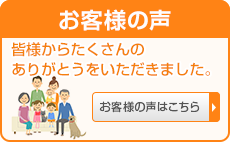事業承継
こちらのページでは、事業承継Q&Aについてご説明いたします。
事業承継についてよくある質問とその解説をまとめましたので、ご参考になさってください。
Q1 事業承継とは、何ですか?
A1 事業承継とは、企業の経営を次世代に引継がせることをいいます。
事業承継の方法としては、以下のような方法があります。
Q2 事業承継の対策は、なぜ必要なのですか?
A2 小規模な会社や、同族会社の場合、後継者を指名しないまま会社経営者が死亡すると、事業の経営権をめぐる争いが生じたり、事業継続が難しくなったりします。
また、会社の株式や事業用の不動産を保有している経営者が、遺言書を作成せず、事業承継対策も行わないまま死亡した場合、誰が会社の株式を相続するのか(遺産の分割方法)について、相続人間で争いが生じることがあります。
Q3 事業承継の対策を立てるために、必要なことは何ですか?
A3 事業承継の対策を立てるためには、会社の現状を把握することが必要です。具体的には、以下の事項の把握・理解が必要です。
① 会社の資産・負債の状況
② 経営者自身の資産・負債の状況
③ 後継者候補の状況
④ 相続の際に予想される問題点はなにか
② 経営者自身の資産・負債の状況は、事業に関連する経営者の資産や負債がどれだけあるのかを判断するために必要です。経営者が保有する会社の株式や事業に使われる経営者個人名義の土地・建物については、経営者が死亡した際に、相続の対象となるからです。
④ 相続の際に予想される問題点は、経営者自身の資産・負債の状況とも関係しますが、法定相続人の把握、法定相続人の人間関係、事業に関する資産の保有状況、相続税額の試算・納税方法などに関する問題点です。経営者の個人資産が、事業用に用いられている場合や、経営者の保有する株式数が多い場合などは、経営者に相続が開始した際に、相続問題が発生する可能性が高くなります。
Q4 親族内で事業承継をする際の注意点を教えてください。
A4 親族内での事業承継をする際には、①後継者の教育、②関係者の理解、③財産の分配についての注意が必要となります。
① 後継者の教育は、社内で経営者が直接教育する方法や、後継者がいったん他社に勤務したり、セミナーに参加するなど社外で教育する方法があります。
② 事業承継の成功には、関係者の理解が必要です。
③ また、経営者の個人資産が、事業用に用いられている場合、経営者が死亡した後の相続を考えて、財産の分配について計画を立てることが必要となります。
Q5 親族内で事業承継をする際の財産の分配は、どのような方法がよいですか?
A5 親族内で事業承継をする際の財産の分配の方法としては、主として経営者が遺言を作成する方法、経営者から後継者に対する生前贈与の方法があります。最近では、民事信託の方法も取られるようです。
 (1)経営者が、事業承継に必要な財産(当該会社の支配株式や事業用不動産等の個人名義資産)を、後継者に全て相続させる内容の遺言を作成することで、後継者に事業承継に必要な財産を集中させることができます。
(1)経営者が、事業承継に必要な財産(当該会社の支配株式や事業用不動産等の個人名義資産)を、後継者に全て相続させる内容の遺言を作成することで、後継者に事業承継に必要な財産を集中させることができます。(2)経営者から後継者に対する生前贈与をすることで、後継者に対して事業承継に必要な財産を集中させることができます。ただし、生前贈与も遺留分による制限を受けることや贈与税の課税に注意してください。
(3)「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」では、後継者が経営者から取得した株式等について、一定の要件の下で,以下の制度を設けています。
①取得株式を遺留分算定の基礎財産に参入しないで遺留分侵害額請求の対象か
(4)後継者自身が、株式を買取るなどの場合には、「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受ければ、日本政策金融公庫などから低金利で融資を受けられます。
(5)相続税法上の制度の中に、事業承継に利用できる制度として以下があります。
Q6 事業承継をする際の財産の分配について配慮する点を教えてください。
A6 後継者への株式や不動産などの事業用の資産を集中させる必要があります。事業承継後に、後継者が安定した事業を行うことができるからです。
後継者へ相当数の株式を集中させ、後継者に株主総会で重要な事項を決議するために必要な3分の2以上の議決権(できれば全株式取得による全ての議決権)を確保することで、安定した経営ができます。
また、経営者の個人資産の不動産が、事業用に使われている場合、この不動産を後継者が取得することで、事業用の土地を確保することができ、安定した経営を図ることができます。
② 後継者への事業用の資産を集中させる際、経営者の死亡後に相続に伴なう問題が生じさせないためにも、後継者以外の相続人への配慮が必要となります。
例えば、後継者に会社株式を全て相続させる遺言をする際には、他の相続人には他の財産(預貯金など)を相続させる内容の遺言をするといった配慮が必要となります。
Q7 民事信託を利用した事業承継の方法を、説明して下さい。
A7 民事信託を利用した方法としては、以下の方法があります。
(1)遺言代行信託
(2)種類株式の代用としての信託
非後継者が取得した受益権の議決権指図権者を後継者とする旨定めておくものです。
Q8 事業承継税制とは何ですか。
A8 上場していない株式についての事業承継には、相続税・贈与税の納税猶予の制度があります。
 (1)「非上場の相続税の納税猶予」とは、経営を承継する相続人等が、承継会社の代表権をもっていた被相続人から相続または遺贈により該会社の株式等を取得した場合、特例非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税申告期限までに一定の担保を提供すれば、経営を承継する相続人の死亡の日まで納税が猶予され、後に経営を承継した相続人が死亡した場合は相続税が免除される制度です。
(1)「非上場の相続税の納税猶予」とは、経営を承継する相続人等が、承継会社の代表権をもっていた被相続人から相続または遺贈により該会社の株式等を取得した場合、特例非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税申告期限までに一定の担保を提供すれば、経営を承継する相続人の死亡の日まで納税が猶予され、後に経営を承継した相続人が死亡した場合は相続税が免除される制度です。(2)「非上場株式の贈与税の納税猶予」とは、経営を承継する人が、承継会社の代表権をもっていた人から該会社の株式で特例対象贈与により取得した場合に、該株式に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、贈与税の申告期限までに一定の担保を提供した場合、贈与者の死亡の日まで納税が猶予され、後に贈与者が死亡した場合(又は、贈与者の死亡以前に承継受贈者が死亡した場合)は、贈与税が免除される制度です。
(3)平成25年に事業承継税制の大幅改正がなされました。この改正は平成27年1月1日以後の相続・贈与に原則適用されます。主な25年改正点を説明します。
①平成25年改正前は、贈与税の納税猶予を受けるためには、現経営者は贈与時に役員を退任することが必要でした。平成25年改正により、贈与時の役員退任要件が「代表者退任要件」に改められ、また役員である贈与者が認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととされました。
②平成25年改正前は、事業承継の納税猶予制度を利用する前に経済産業省の「事前確認」が必要でした。平成25年改正により、平成25年4月1日以降は経済産業省の「事前確認」を受けていなくても、事業承継の納税猶予制度を利用できるようになりました。
③平成25年改正前は、雇用の8割以上を5年間毎年維持することが、必要でした。平成25年改正により、納税猶予の取消事由となる雇用確保要件について、雇用の8割以上を「5年間平均」で評価することに緩和されました。
④平成25年改正前は、納税猶予の適用対象者は、現経営者の親族に限定されました。
⑤平成25年改正前は、納税猶予額の計算で、現経営者の債務・葬式費用を株式評価額から控除することになっていたため、納税猶予額が少なく算出されることが少なくありませんでした。平成25年改正により、現経営者の債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除する方法になったため、株式の納税猶予をフル活用できるようになりました。
⑥平成25年改正前は、納税猶予制度適用後に、資産保有会社に該当するなどして、納税猶予の打ち切りになると、納税猶予額に加え、利子税の支払いが必要でした。
(4)平成30年事業承継税制が改正されました。
平成30年改正では、一定の要件のもとで認められている現行事業承継税制(納税猶予制度)について10年間に限って 大幅な改正を盛り込んだ新制度が創設されます。なお、平成30年の制度は、現行制度との選択適用になります。
平成30年の改正では、会社を自主解散したり、親族以外の人に会社を譲渡(M&A等)する際には、解散・譲渡時の株価を基に相続税額を再計算して、これまでの全額納付に比べて税負担が減少する仕組みが導入されます。
現行では、特例の適用が受けられるのは、原則として、一人の先代経営者から一人の後継者への事業承継が対象とされています。平成30年の改正では、これまでの原則的な事業承継に加えて
a複数人からの事業承継
b複数人(最大3人)への事業承継 等の幅広いパターンの事業承継が特例適用の対象とされます。
事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から贈与者の子や孫でない20歳以上の後継者への贈与も相続時精算課税制度の対象となります。
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
 当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。