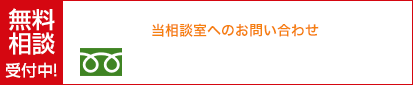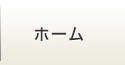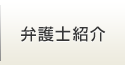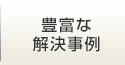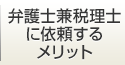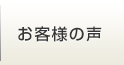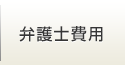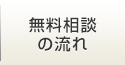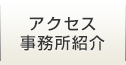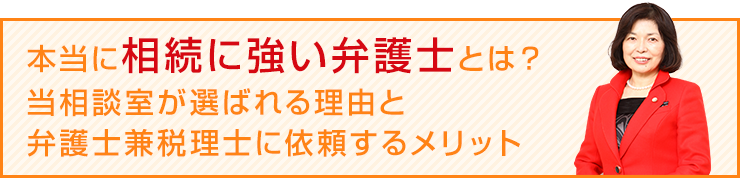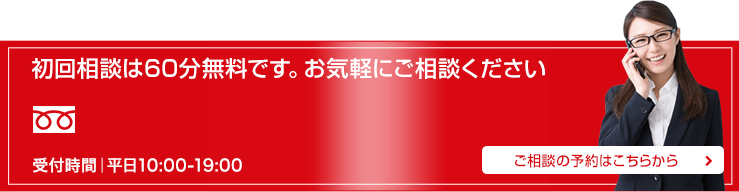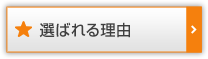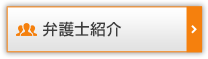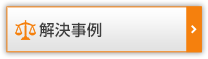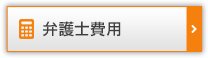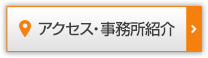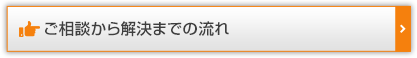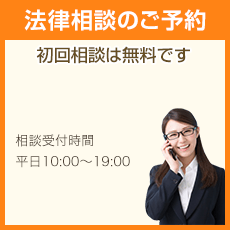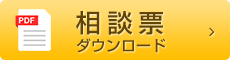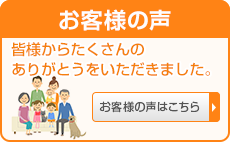認知症の方が作成した遺言が無効となる場合、有効となる場合とは?相続に詳しい弁護士が判例と併せて紹介
認知症と遺言無効
認知症の方が作成した遺言書は、遺言能力が欠けるために無効となることがあります。
しかし、認知症と診断された方が作成した遺言書のすべてが無効となるわけではありません。
こちらのページでは、遺言能力とは何かについて詳しく解説した上で、認知症と遺言の有効性との関係性についてお伝えいたします。
有効な遺言をするには遺言能力が必要
法律上、有効な遺言をするためには、遺言能力が必要とされています。
そもそも遺言とは、相続人(亡くなった方)が生前に、自分の財産を、誰にどれだけ渡したいのかについて意思表示をすることです。
しかし、このように重要な意思表示をするためには、一定程度の理解力や判断力があることが前提となります。重度の認知症や知的障害などを抱えた方や、幼い子どもなどが作成した遺言書を、そのまま有効なものとして認めてしまうと、本来なら遺産を受け取るべき相続人が遺産を受け取れなくなるなどの不都合が生じてしまいます。
そのため、遺言能力のない方が作成した遺言書は無効と判断されるのです。
近年は高齢化社会が急速に進展し、認知症の診断を受ける方が増えていることから、「認知症の人が作成した遺言書は有効か」や、「認知症の診断を受けた後は遺言書を作成できないのか」といった問題がクローズアップされています。
遺言能力とは
遺言能力とは、遺言の内容と、その遺言によって生じる法律的な効果を理解した上で、自分が意図したとおりの遺言内容を正しく意思表示できる意思能力のことです。
民法では満15歳以上の人に原則として遺言能力が認められていますが、満15歳以上の人であっても、上記の意思能力を失っている場合には遺言能力が否定されます。
認知症を発症すると意思能力は低下してしますが、その程度はさまざまですので、認知症の診断を受けたからといって、必ずしも遺言能力が認められないわけではありません。
また、遺言能力の有無は画一的に判断されるのではなく、遺言内容との関係で相対的に判断されることにも注意が必要です。
比較的簡易な内容の遺言では意思能力が低くても遺言無効とされにくいですが、複雑な内容の遺言になると、高度の意思能力がなければ遺言無効と判断されやすい傾向にあります。
したがって、認知症の方が作成した遺言書の有効性を判断する際には、遺言書を作成した当時の遺言者の意思能力の程度と、遺言の内容とを総合的に考慮することが重要です。
認知症の方の遺言が無効になるケース
次に、認知症の方の遺言能力が否定され、その遺言が無効になるケースをご紹介します。
症状の程度が重い
重度の認知症で、日常的な会話も困難な状態の方が作成した遺言書は、無効と判断される可能性が高いです。
一方、軽度の認知症で、物忘れなどの症状が見られるものの、会話はほぼ通常どおりにできる状態であれば、その方の作成した遺言書は有効と判断される可能性が十分にあります。
遺言の有効性を認めてもらうためには、遺言書が作成された前後の時期に、遺言者が遺言能力を有していたことを証明できる客観的な資料を、できる限り多く収集することが重要です。
例えば、医師の診断書や、入通院していた医療機関のカルテ、老人ホームや介護サービスを利用していた場合には、入所記録や介護サービス記録などを入手することが考えられます。
さらに、主治医の意見書や介護担当者などの報告書、本人の生活状況を記録した動画なども有力な資料となることがあります。
遺言の内容が複雑
遺言の内容が複雑であればあるほど、認知症の方が作成した遺言書は無効と判断される可能性が高まります。
この点、例えば、「妻(または夫)にすべての財産を譲る」というような単純な内容の遺言であれば、本人の意思能力がある程度低下していたとしても、その遺言は有効と判断される可能性が十分にあります。
しかし、多種多様な遺産が豊富にあり、財産を譲る相手の人数も多く、遺産の分け方が細かく指定されているような場合には、かなり高度の意思能力が残っていたことを証明できなければ、その遺言は無効と判断される可能性が高いです。
遺言の内容に合理性が乏しい
遺言の内容に合理性があるかどうかも、認知症の方が作成した遺言書の有効性に影響を及ぼすことがあります。
例えば、長年一緒に暮らしてきた配偶者や長男などに「すべての財産を譲る」という内容の遺言には、合理性が認められます。このような遺言書は、認知症の方が作成したものであっても、有効と判断されやすくなります。
しかし、何十年も交流がなかった親戚などに遺贈する内容の遺言には、特別な事情がない限り、合理性は認められません。したがって、このような遺言書は無効と判断されやすいです。
認知症の遺言に関する判例紹介
近時の判例において、認知症の遺言者について、遺言能力を否定する判例が、地裁高裁でいくつも出ていますが、主な高等裁判所の判例をいくつか紹介します。
なお弁護士法人リーガル東京は、認知症であった遺言者の遺言能力が争われた訴訟をいくつも経験しております。
◎遺言者が認知症だったので遺言無効としたい方
◎遺言者が認知症なので遺言無効を主張され困っている方
いずれの場合でも豊富な経験に基づいてアドバイスいたします。
(1)東京高裁平成25年3月6日判決
事案の概要
甲(元医師)は、昭和55年4月25日付で、全財産を妻乙に相続させる旨の自筆証書遺言(旧遺言)をしていました。ところが、その後、妻乙が存命中である平成19年3月2日「甲の財産を妹丙に相続させ、丙を祭祀承継者及び遺言執行者とする」という内容の公正証書遺言をしていました(本件遺言)。甲は平成19年8月27日に死亡し(82歳)、妻乙は同年4月21日に死亡(79歳)しました。甲の法定相続人は、その弟丁1、平成20年1月22日に死亡した別の弟の妻丁2、妹の丁3と丙でした。
丙は、丁らに対し、本件遺言が有効であることの確認を求める訴訟を提起しました。これに対し、丁らは、本件遺言当時、甲が重度のうつ病、認知症であり、平成19年2月22日以降、高熱を出して不穏行動を繰り返し、重篤な肺炎に罹患し危機的状況にあったから、遺言能力はなく、妻乙の生存中に妹である丙に全財産を相続させるとの遺言をするはずがない旨主張して、その有効性を争いました。
本判決の概要
本判決は、甲の経歴、生活状況、病院への入院・転院、入院中の様子、乙の状況、甲の介護老人保健施設入所中の様子などにつき詳細に事実認定したうえで、甲は本件遺言時に遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力たる意思能力を備えておらず、遺言能力があったとはいえないから、本件遺言は有効とは認められない旨判示して、本件遺言を有効とした第一審判決を取消し、丙の請求を棄却しました。
(2)東京高裁平成25年8月28日判決
事案の概要
Z(昭和19年生)は、平成22年8月に死亡しました。Xは、Zの子であり、Zの唯一の法定相続人です。Y1、Y2はZの従姉妹であり、Y3はY1の子である。ZがYらに対し、財産を遺贈する内容の公正証書遺言(以下「本件遺言書」といいます。)を作成していました。本件遺言書は、Zが末期ガンによる死亡6日前に作成されたものであることから、遺言能力の欠如等により無効であるとして、Zの子Xが、本件遺言書の無効確認を求めた事案です。
本判決の概要
本判決は次の理由から、Zには当時遺言能力はなかったと判示しました。
①Zは、進行癌による疼痛緩和のため、平成22年2月末ころから、K病院より麻薬鎮痛剤を処方されるようになり、同年7月23日に同病院に入院した後は、せん妄状態と断定できるかどうかはともかく、薬剤の影響と思われる傾眠傾向や精神症状が頻繁に見られるようになったこと
②本件遺言作成時のZの状況も、公証人の問いかけ等に受動的に反応するだけであり、公証人の案文読み上げ中に目を閉じてしまったりしたほか、自分の年齢を間違えて言ったり、不動産を誰に与えるかについて答えられないなど、上記の症状と同様のものが見受けられたこと
③本件遺言の内容は、平成22年1月時点でのZの考えに近いところ、Zは同年7月に上記考えを大幅に変更しているにもかかわらず、何故、同年1月時点の考え方に沿った本件遺言をしたのかについて合理的な理由は見出しがたいこと
以上により、Zには本件遺言書作成当時、遺言能力がなかったと判断し、Xの請求を認容した原判決の結論を支持し、Yらの控訴を棄却しました。
(3)東京高裁平成22年7月15日判決
事案の概要
本件は、87歳であった亡Aの全財産を妹Yに遺贈する旨の公正証書による遺言につき、Aの養子X1X2が、本件公正証書はAの意思によらずに作成され、Aは作成当時認知症が進行し遺言能力を欠き、本件遺言は無効であると主張して、遺言無効確認及びYが本件遺言に基づいてした所有権移転登記の抹消登記手続を求めた事案です。
判決の概要
本判決は、本件公正証書の作成がAの意思に基づくものであることは認めましたが、Aには認知症と見られる症状が次第に進行し医師により認知症と診断されたこと、骨折により入院し退院後も介護老人保健施設への入所を続け、本件遺言時のAの認知症の症状は診断時よりも進行していたものと認められること、Aが強く示した意向は認知症による被害妄想の表れとみることができること等から、本件遺言は無効であると判断し、公正証書作成当時司法書士2名が立ち会っているものの、司法書士は当日Aに初めて会ったものであり、医師や介護施設職員の意見を聴取していないことからすると、司法書士がAとの会話の受け答えに基づいてAに遺言能力があると感じたとしても、これによって上記認定が妨げられることはないとしました。
(4)東京高裁平成21年8月6日判決
事案の概要
亡父A(大正2年生、平成17年5月に91歳で死亡)は、子Yに全財産を相続させる平成13年3月1日付け自筆証書遺言(本件遺言。遺言時87歳)を作成していました。亡Aの子であるXらが、Yに対し、本件遺言が無効であるとして、その無効確認を求めました。
判決の概要
控訴審では、Aが入通院していた病院、診療所の診療録、デイサービス記録等に基づき、老人医療の専門医によるAの遺言能力についての鑑定が行われ、鑑定人は、Aは平成8年ころに発病したと思われるアルツハイマー病があり、平成9年9月30日に生じた左脳脳梗塞の合併で痴呆が重症化し、平成10年以降も痴呆は緩徐に進行し、平成12年6月ころまでにはやや高度の痴呆状態に至り、平成13年以降も進行があり、平成15年以降衰弱が目立ち、平成17年5月15日に心不全、呼吸不全で死亡したもので、平成10年から平成15年までの間に痴呆は改善の兆しがなく次第に重くなる経過をたどったものであり、Aは本件遺言書を作成したとされる平成13年3月当時にはアルツハイマー病と脳梗塞の合併した混合型痴呆症に罹患しており、やや重い痴呆状態にあったもので、自らの意思で遺言を思い立ち、遺言内容を考えて遺言をするという能力に欠けていたと判断しました。
認知症に関する遺言無効の解決事例は以下をご覧ください。
認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例判決
認知症の方の遺言書作成時の注意点
認知症と診断された方が遺言書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
遺言能力を証明できる資料を準備する
遺言の有効性が争われた場合には、有効であることを主張する方が、遺言能力を証明できる資料を準備しなければなりません。
しかし、遺言者の死後に、遺言当時における本人の意思能力の程度を証明できる客観的な資料を収集するのは、難しい場合もあるでしょう。
そのため、遺言書を作成する時点において、十分な意思能力が残っていることを証明できるだけの資料を収集し、残しておくことが重要となります。
基本的には、医師に診断書を発行してもらったり、入通院している病院の診療記録や、介護認定の資料を入手しておいたり、長谷川式認知症評価スケール(HDS-R)の検査やMMSE(ミニメンタルステート検査)の検査やMRI(磁気共鳴画像法)の検査を受けたりして、その診療記録を入手しておくことが有効です。
これらの書類の内容から意思能力が争われそうと考えられる場合は、上記のような認知症の専門医による診断書を入手して保存しておくことの他に、主治医の意見書や介護担当者の報告書を作成してもらったり、本人の生活状況を動画に撮影して保存したりしておくなどして、資料の補充を検討するとよいでしょう。
公正証書遺言を作成する
認知症の方が遺言をする際には、公正証書遺言を作成するのが有効です。
公正証書遺言を作成する際には、遺言者が公証人と面談し、遺言の内容を確認されます。そのとき、遺言者が遺言の内容を理解していないようであれば、公正証書遺言は作成してもらえません。
また、公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人が立ち会い、遺言者が正常な精神状態で遺言したかどうかを確認することとされています。
したがって、公正証書遺言が作成された以上は、遺言能力があった可能性が高いと考えられるため、その遺言は有効と判断されやすくなります。
ただし、公証人や証人は、遺言者の意思能力の有無や程度について、を医学的な見地から判断できるわけではありません。そのため、公正証書遺言が無効と判断された裁判例も存在することには注意が必要です。
このようなリスクもあるので、公正証書遺言を作成する場合でも、その時点での遺言能力を証明できる資料を収集し、残しておくことは重要です。
弁護士に相談する
認知症の方が作成した遺言書の有効性は、遺言当時の本人の意思能力の有無や程度、遺言の内容などを総合的に考慮した上で、最終的には法的な見地から判断されます。
そのため、遺言書を作成する際には弁護士に相談することをおすすめします。
自己判断で遺言書を作成すると、後に遺言が無効と判断されるリスクが高まりますが、弁護士に相談することで、有効な遺言書を作成するための具体的なアドバイスが受けられます。
弁護士に依頼するメリット
遺言書の作成を弁護士に依頼すれば、遺言能力に関する資料を収集する段階からサポートが受けることが可能です。
そして、弁護士は、得られた資料を参照し、遺言能力があるかどうかを的確に判断します。もし、複雑な内容の遺言をするだけの遺言能力がないと考えられる場合には、遺言の内容を簡素化することによって、有効な遺言書を作成するなどのアドバイスもしてくれます。
万が一、遺言者の死亡後に遺言の有効性を争われた場合にも、弁護士が資料に基づき、遺言が有効であることを主張・立証してくれます。
認知症の診断を受けた後に遺言書の作成をお考えの方や、遺言の有効性を争われてお困りの方は、お早めに弁護士へご相談ください。
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。