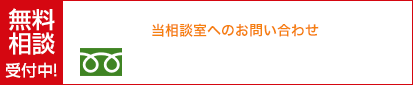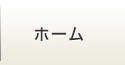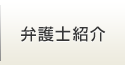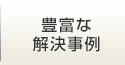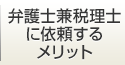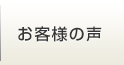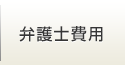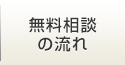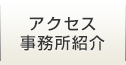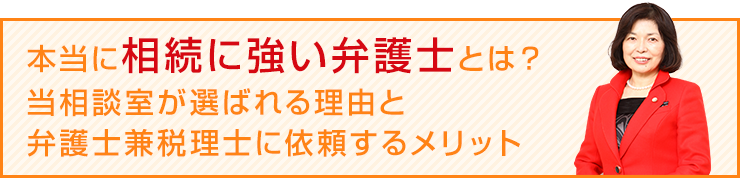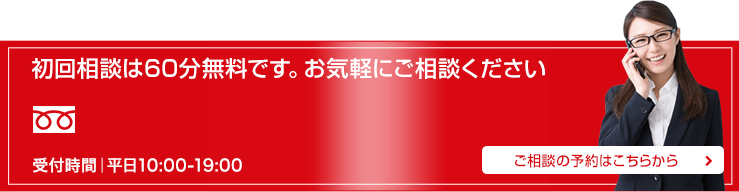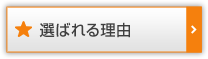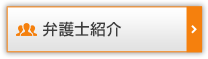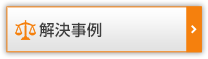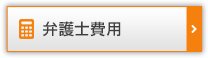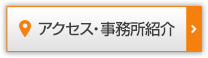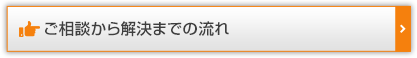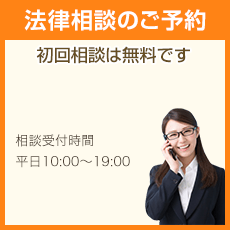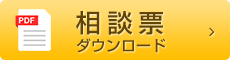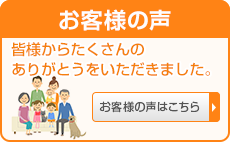遺産分割の種類について
文責:弁護士 小林幸与
こちらのページでは、遺産分割の種類についてご説明いたします。
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人間で分割することですが、遺産の中には、不動産のように物理的に分割することが難しいものもあります。そんなときは、分割方法を工夫することが必要です。
遺産の分割方法は4種類あり、状況に応じて最適な分割方法を選ぶことで、納得のいく遺産分割が可能となります。
以下で、遺産分割の種類について詳しくみていきましょう。
1.遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を、相続人間で分け合うことです。
遺言書で遺産の分割方法が指定されている場合は、基本的にその内容どおりに遺産を分割します。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、どの相続人がどの遺産を引き継ぐかを決めなければなりません。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺言書がある場合でも、遺産分割協議によって相続人全員が合意すれば、遺言書による指定とは異なる内容で遺産を分割することが可能です。
遺産分割協議が必要なケースで、相続人間の話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停または審判を申し立て、家庭裁判所の手続きを通じて遺産の分割方法を決めることになります。
2.遺産分割の4つの種類と特徴
それでは、4種類の遺産分割について、それぞれの内容と特徴をみていきましょう。
現物分割
現物分割は、遺産を現物のままの状態で分け合う方法です。
例えば、「預貯金のうち、500万円を妻に、250万円を長男に、250万円を二男に相続させる」というように、預貯金や現金など現物で分割可能なものは、現物分割の方法によることになります。
土地や建物といった不動産は物理的に分割することが困難ですが、他にも多くの遺産がある場合には、現物分割が可能なケースもあります。例えば、「自宅は妻に、預貯金は長男に、有価証券は二男に相続させる」といったケースでは現物分割が可能です。
また、土地については、分筆して分け合うことで現物分割をすることもできます。
代償分割
代償分割は、現物分割が困難な遺産を特定の相続人が現物で取得し、法定相続分を超えた取得分に相当する金銭を、代償金として他の相続人へ支払う方法です。
こうすることで、遺産となった不動産を手元に残したまま、公平に遺産を分割することが可能となります。
被相続人が所有していた自宅に住み続けたい相続人がいる場合や、事業用不動産を引き継ぎたい相続人がいる場合などでは、代償分割の方法が有効です。
ただし、不動産の他に高価な遺産がない場合には、不動産を取得した相続人が多額の代償金を用意しなければなりません。代償金を支払えなければ、他の方法で遺産を分割せざるを得ないこともあります。
換価分割
換価分割は、不動産などの遺産を売却し、得られた代金を分け合う方法です。
遺産の中に不動産があったとしても、売却すれば金銭を分け合うことになりますので、公平な遺産分割が可能となります。
ただし、遺産となった不動産を手元に残すことはできませんので、被相続人が所有していた自宅に住み続けたい相続人がいる場合などでは、じっくりと話し合う必要があるでしょう。
また、不動産などを売却するためには、時間や労力だけでなく、ある程度の経費がかかることに注意が必要です。売却価格によっては譲渡税(所得税・住民税)がかかることもありますので、注意しましょう。
共有分割
共有分割は、不動産などの遺産を、複数の相続人の共有として引き継ぐ方法です。各相続人の持ち分は、基本的に法定相続分に従って決めることになります。
この方法によれば、不動産などの遺産を手元に残しつつ、公平に遺産を分割することが可能となります。
しかし、不動産を共有名義にすると、売却や大規模なリフォームをする際に共有者全員の合意が必要なるため、不動産の利用や運用が難しくなることがあります。
また、共有者の誰かが亡くなるたびに新たな相続が発生して共有者が増え、権利関係が複雑になっていきます。
このような事情によってトラブルが発生しやすいため、実務上、共有分割の方法はあまりおすすめできません。
3.遺産分割でよくあるトラブル
ほとんどの場合、遺産分割は現物分割、代償分割、換価分割のどれかの方法で行うことになりますが、次のようなトラブルも発生しやすいため、注意が必要です。
不動産の分割方法でもめる
遺産の中に不動産がある場合、その分割方法でもめるケースが多いです。
利便性の高い不動産や、思い入れのある自宅が遺産となった場合、誰がその不動産を取得するかでもめることがあります。
空き家となった自宅については、「将来的に自分が住むかもしれないから残しておきたい」と主張する相続人がいる一方で、手っ取り早く金銭を受け取りたい相続人が「早く売却すべきだ」と主張するようなケースも見受けられます。
このように相続人間で意見が対立することが多いですが、全員が合意するまで遺産分割協議は成立せず、遺産を分け合うことはできません。
不動産などの評価額でもめる
不動産の遺産分割では、その不動産の評価額をめぐってもめることも多いです。
代償分割の方法による場合は、その不動産の評価額によって代償金の金額が決まります。
しかし、遺産分割における不動産の評価方法は法律で定められておらず、実務で用いられている評価方法は複数あります。
そして、不動産を取得する相続人としては、評価額が低いほど有利になります。逆に、代償金を受け取る立場の相続人としては、評価額が高いほど有利になります。このような思惑から、各相続人が自分に有利な評価方法を用いるべきだと主張し、意見が対立することになりやすいのです。
適正な評価額を求めるためには不動産鑑定を実施することが最も望ましいですが、1カ所につき五十万円以上の費用を要することが多いです。
そのため、実務上は各相続人がそれぞれ別の不動産会社へ簡易査定を依頼し、その平均査定額を評価額とすることに合意するケースが多くなっています。
特別受益や寄与分でもめる
特別受益や寄与分は相続分に影響を及ぼすため、遺産分割でもめやすい問題です。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた、特別な生前贈与や遺贈のことです。特別受益がある場合の遺産分割では、相続人間の公平を図るために、特別な利益を受けた相続人の取り分は減り、他の相続人の取り分は増えることになります。
一部の相続人だけが、学費や事業資金などで被相続人が多額の支援を受けていたような場合は、他の相続人が特別受益を主張してもめることになりがちです。
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人がいる場合に、その貢献度に応じて、その相続人の取り分を他の相続人の取り分よりも多くすることをいいます。
被相続人の事業を手伝ったり、療養看護に努めたりした相続人がいる場合は寄与分が認められる可能性がありますが、「特別の貢献」をしたとまではいえないケースでは、寄与分が認められません。
「特別の貢献」をしたと認められるケースでも、寄与分を具体的な金額に換算することは意外に難しい問題です。
代償金を支払えない
代償分割する場合には、不動産などを取得した相続人の支払い能力が問題となることもあります。
例えば、評価額5,000万円の自宅と預貯金1,000万円の遺産を、被相続人の妻と長男、二男で分けるとしましょう。
代償分割で妻が自宅を取得するとすれば、妻は長男と二男に対して合計2,000万円もの代償金を支払う必要があります。支払えない場合には、やむを得ず自宅を売却せざるを得ないこともあるでしょう。
相続人が妻と子どもの場合は、子どもが代償金の支払いを猶予してくれることも少なくありません。しかし、子どもがおらず、妻と被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人となる場合には、トラブルに発展する可能性が高くなります。
協議に応じない相続人がいる
遺産分割をしようとしても、協議に応じない相続人がいることも少なくありません。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、協議に応じない相続人を除外して手続きを進めることはできません。
どうしても協議に応じない相続人がいる場合には、遺産分割調停または審判を申し立てて、家庭裁判所の手続きを通じて解決を図ることになります。
行方不明の相続人がいる場合には、失踪宣告や不在者財産管理人選任の申し立てをすることにより、遺産分割の手続きを進めることが可能です。
4.遺産分割について当事務所に相談するメリット
当事務所の弁護士は、相続と不動産に関する問題を中心に取り扱っていますので、不動産の遺産分割方法でお悩みのご相談者様には最適なご提案をさせていただくことが可能です。
ご依頼いただければ、遺産の評価から他の相続人との協議、家庭裁判所での調停・審判に至るまで、全面的にお任せいただけます。
これまでに500件以上の相続トラブルを解決に導いてきた実績がございますので、複雑な案件や、相続人同士の対立が激しい案件でも、解決までフルサポートさせていただきます。
初回のご相談は60分まで無料で対応しておりますので、遺産分割でお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。