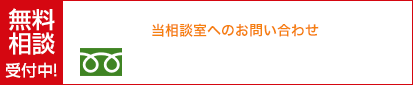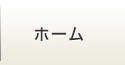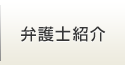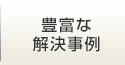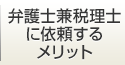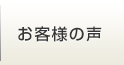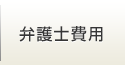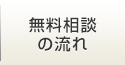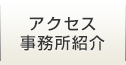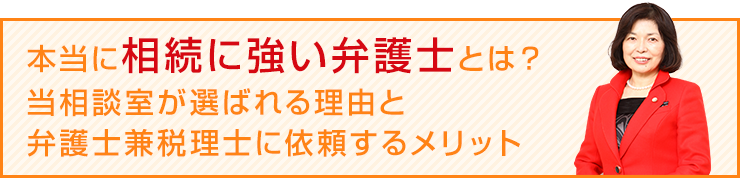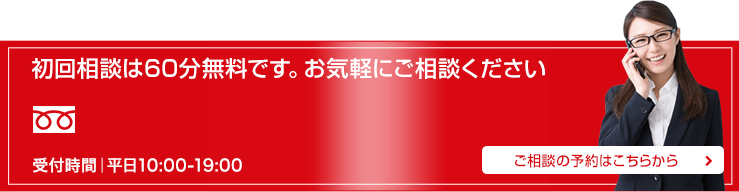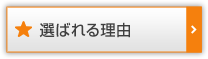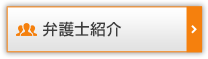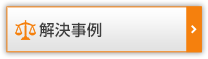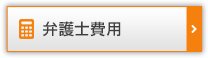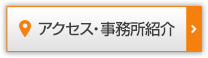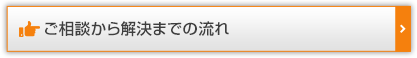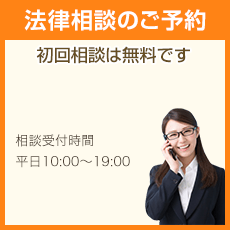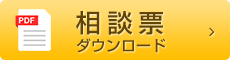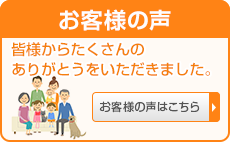遺留分侵害額請求とは?相続に詳しい弁護士が解説
遺留分侵害額請求とは
遺言や生前贈与は相続トラブルの防止に役立つものですが、その内容によっては相続人間に著しい不公平が生じ、逆に激しい相続トラブルを招くこともあります。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分として最低限の相続分が保障されています。遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合でも、遺留分侵害額請求を行うことで、最低限の遺産を取得することが可能です。
この記事では、遺留分侵害額請求の概要や、手続きの流れについてわかりやすく解説します。
※遺留分侵害額請求は2019年7月の相続法改正によって定められました。それ以前は遺留分減殺請求でした。したがって、2019年6月末までに開始した相続には遺留分減殺請求が適用されます。
1.遺留分とは
まずは、遺留分侵害額請求の「遺留分」とは何かを理解しておきましょう。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、遺言をもってしても奪われることのない相続分のことです。
具体的には、以下の相続人に遺留分が認められます。
・配偶者
・直系卑属(子ども、孫など)
・直系尊属(両親、祖父母など)
兄弟姉妹、およびその代襲相続人となる甥・姪には遺留分が認められていません。
遺留分としてどれだけの相続分が保障されているのかというと、法定相続分に以下の割合をかけることで算出できます。
・直系尊属のみが相続人となる場合:3分の1
・その他の場合:2分の1
例えば、父が5,000万円の財産を残して亡くなり、妻と子2人が相続人となる場合、各相続人に認められる遺留分は以下のようになります。
・妻:5,000万円×法定相続分(1/2)×1/2=1,250万円
・子(1人あたり):5,000万円×法定相続分(1/4)×1/2=625万円
2.遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分を取り戻すための手続きです。以下で、具体的にみていきましょう。
遺留分侵害額請求の概要
遺留分侵害額請求は、被相続人(亡くなった方)が行った遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合に、受遺者(遺言によって遺産を取得した人)や受贈者(生前贈与によって財産を取得した人)に対して、侵害された金額の支払いを求めるものです。
特定の遺産の取得を主張できる権利ではなく、遺留分に相当するお金の取り戻しを請求できる権利であることにご注意ください。
例えば、先ほどのケースで亡き父が「長男にすべての財産を譲る」という遺言を残していた場合、妻は遺留分侵害額請求によって「自宅を取得したい」と主張することはできません。あくまでも、遺留分に相当する1,250万円という金銭の支払いを、長男へ請求することになります。
遺留分侵害額請求の対象となる場合
遺留分侵害額請求の対象となるのは、以下の行為によって遺留分が侵害された場合です。
・遺言による相続分の指定:「長男にすべての財産を譲る」などの不公平な遺言
・遺贈:遺言によって法定相続人以外の人に財産を譲ること
・死因贈与:贈与者の死亡を条件として財産を贈与すること
・生前贈与:被相続人が生前に財産を贈与すること
生前贈与については、以下の制限があることに注意が必要です。
・法定相続人以外の人への生前贈与については、相続開始前の1年間に行われたものに限る
・法定相続人への生前贈与については、相続開始前の10年間に行われたものに限る
・生前贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は、贈与の時期を問わない
「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合」とは、不相当な対価での有償行為が行われた場合のことを指します。
分かりやすくいうと、例えば2,000万円の不動産を100万円で売却したような場合です。この場合には、差額の1,900万円は贈与とみなされ、有償行為が行われた時期を問わず、1,900万円が遺産総額に加算されます。
なお、遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与には、以下の順序があります。
①受遺者と受贈者とがいるときは、先に受遺者へ請求する
②受遺者が複数あるときは、その目的の価額に応じて各受遺者へ請求する(ただし、遺言で別段の意思表示がある場合は、その意思に従う)
③受贈者が複数いて、その贈与が同時にされたものであるときも、その目的の価額に応じて各受贈者へ請求する(ただし、遺言で別段の意思表示がある場合は、その意思に従う)
④受贈者が複数いるとき(③の場合を除く)は、後に贈与を受けた者から先に、順次請求する
遺留分侵害額請求の対象とならない場合
以下の場合は、遺留分が侵害されていても遺留分侵害額請求の対象とはなりません。
・時効が完成した場合
・遺留分を放棄した場合
・遺産分割協議が成立した場合
遺留分侵害額請求権は、次の期間が経過すると消滅時効にかかり、その後は行使できなくなります。
・相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
・相続開始のときから10年
遺留分を放棄することは可能ですが、被相続人の生前に放棄するためには、家庭裁判所に申し立てをして許可を得なければなりません。そのため、自分の意思に反して遺留分の放棄を強制されることはないといえます。
また、遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、遺留分権利者の任意です。遺留分侵害額請求権を行使せずに遺産分割協議が成立してしまった後は、相続人全員の合意がない限り、遺産分割協議の内容を覆すことはできません。
3.遺留分侵害額請求の手続きの流れ
遺留分侵害額請求の手続きは、以下の流れで進めていきます。
話し合い
まずは、遺留分を侵害した相手と話し合ってみましょう。相手の理解が得られたら、合意によって解決することができます。穏便に解決するためには、双方が譲り合って妥当な金額で合意するのもよいでしょう。
ただし、一般的には遺留分について理解している人が少ないこともあり、この話し合いは揉めることが多い傾向にあります。
話し合いが平行線になると、消滅時効が完成してしまう可能性がありますし、遺産を使い込まれて取り戻しが困難となるおそれもあります。
スムーズに話し合えない場合は自力で無理をせず、早めに弁護士へご相談の上、次のステップに進むのがおすすめです。
内容証明郵便の送付
話し合いがまとまらなかった場合は、遺留分侵害額請求書を作成し、内容証明郵便で相手宛に送付しましょう。
内容証明郵便とは、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送付したのかを、郵便局が公的に証明してくれるものです。内容証明郵便を送付しておけば、後の訴訟で証拠として使用できます。
配達証明をつけておけば到達日も証明されるので、時効期間内に権利を行使したことの証拠にもなります。
このような格式のある書面を送付することで、相手に心理的な圧力をかけることができますので、話し合いを有利に進めやすくなる効果も期待できるでしょう。弁護士名義で内容証明郵便を送付すれば、この効果がさらに高まります。
調停
どうしても話し合いで解決できない場合には、法的手続きが必要になります。
ただし、遺留分侵害額請求については親族間の問題であることから、訴訟を提起する前に原則として家庭裁判所へ調停を申し立てなければならないこととされています。このことを「調停前置主義」といいます。
調停では、家庭裁判所から選任された調停委員が、中立公平な立場で話し合いを仲介してくれます。そのため、当事者だけで話し合うよりも合意に至りやすいというメリットが得られます。
ただし、あくまでも調停は話し合いの手続きですので、遺留分の取り戻しを強制的に実現することはできません。
調停でもスムーズに話し合えない場合は、早めに見切りをつけて訴訟に進む方が得策といえます。
なお、遺留分についての話し合いの段階で、弁護士に依頼して交渉しても解決できなかった場合は、調停申し立てをしないで、遺留分侵害額請求の訴訟提起することもできます。
訴訟
弁護士に依頼したが、交渉が上手くいかなかった場合、または、調停が成立しなかった場合は、訴訟を提起することになります。遺留分侵害額請求訴訟を提起する先は家庭裁判所ではなく、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所です。
訴訟では、自分が主張する事実を証明するための証拠が必要です。特に、遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われた事実や、その目的物の価額を証明できる証拠が重要となります。
証拠がそろっていれば、判決により強制的に遺留分を取り戻すことが可能となります。判決前に和解協議を行うことも可能なので、相手が敗訴を恐れて歩み寄ってきた場合は、和解で解決するのもよいでしょう。
4.遺留分侵害額請求を自分で行う場合のデメリット
遺留分侵害額請求の手続きは、弁護士に依頼するのがおすすめです。自分で手続きを行う場合には、以下のデメリットがあることにご注意ください。
手間がかかる
遺留分侵害額請求の手続きには、手間がかかります。
まず、遺留分が侵害されたかどうかを判断するために、遺言書を確認するだけでなく、生前贈与や死因贈与が行われていないか、行われている場合はその内容や、生前贈与の時期も調査しなければなりません。
さらに、遺留分侵害額を算出するために、すべての遺産について評価額を調査することも必要です。
その上で証拠を確保し、遺留分を侵害している相手に連絡して話し合うことになります。話し合いがスムーズに進めばよいですが、意見が対立する場合には難航し、多大な手間と時間を要することが多いです。
時効に注意する必要がある
遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年という短期間で消滅時効にかかってしまいます。
そのため、手続きに手間取っていると気づかないうちに消滅時効が完成するおそれもあることに注意が必要です。
揉める可能性がある
遺留分侵害額請求に関する話し合いは、先ほどもご説明したように揉める可能性が高いです。
こちらは法律の規定に従って権利を主張しているだけでも、相手に法律の知識が乏しい場合には話し合いが平行線となり、感情的なトラブルに発展することもあるでしょう。
それまでは円満だった親族関係も、遺留分侵害額請求を行うことで対立し、親族関係に深い溝が生じることにもなりかねません。
5.弁護士に相談するメリット
遺留分侵害額請求で弁護士に相談すれば、まず、遺留分侵害額請求権を行使できるかどうか、行使できる場合はいくらくらい請求できるかについて、的確なアドバイスが得られます。
遺留分侵害額請求を行うことになった場合は、弁護士に依頼すれば、すべての手続きを代理人としてサポートしてもらえるので、手間を省くことができます。
相手と揉めそうな場合でも、弁護士が間に入って冷静かつ論理的に相手を説得すすることで、穏便に解決できることもよくあります。
話し合いがまとまらない場合でも、弁護士が訴訟の手続きを迅速に進めてくれるので、早期の解決が期待できます。
また、時効期間が間近に迫った場合でも、弁護士に相談すれば早急に内容証明郵便を送付してもらえるので、時効を止めることが可能です。
遺留分を侵害されてお困りの際は、一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。